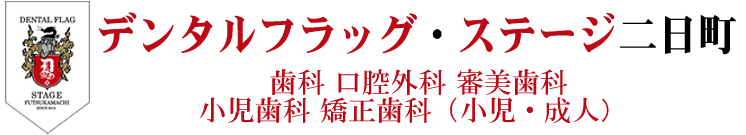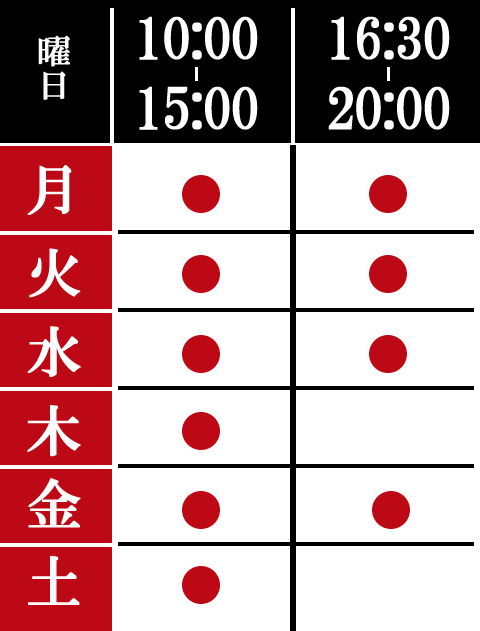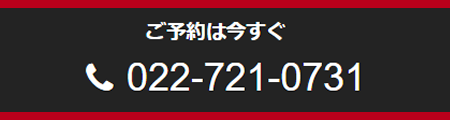みなさんは「朝起きたら顎が疲れている」「歯がすり減っている気がする」「肩こりや頭痛が続く」と感じたことはありませんか? それは 歯ぎしり(ブラキシズム) の可能性があります。
歯ぎしりは多くの人が無意識に行っており、軽度であれば問題にならないこともありますが、 強い歯ぎしりを放置すると歯や顎、全身の健康に深刻な影響を及ぼすことがあります。
今回は、歯ぎしりの悪影響や原因、対策について詳しく解説していきます。
【1. 歯ぎしりとは?】
歯ぎしり(ブラキシズム)とは、 無意識のうちに強く歯をこすり合わせたり、食いしばったりする動作 のことを指します。特に、睡眠中に起こることが多く、自分では気づきにくいのが特徴です。
歯ぎしりには以下の3種類があります。
1. グラインディング(歯をギリギリと擦り合わせるタイプ)
2. クレンチング(強く噛みしめるタイプ)
3. タッピング(歯をカチカチと打ち鳴らすタイプ)
特に グラインディングやクレンチングは歯や顎に大きな負担をかけるため、早めの対策が必要です。
【2. 歯ぎしりの悪影響】
① 歯がすり減る・割れる
歯ぎしりによって 歯の表面(エナメル質)が削れてしまう ため、次第に象牙質が露出し、知覚過敏を引き起こします。冷たいものや熱いものがしみるようになったら要注意です。
さらに、歯ぎしりの強い力で 歯にヒビが入ったり、最悪の場合、割れてしまったりすることも あります。歯が割れると、抜歯が必要になるケースもあるため、早めの対策が大切です。
② 顎関節症(がくかんせつしょう)のリスク
歯ぎしりは 顎の関節や筋肉に過剰な負担をかける ため、顎関節症を引き起こす原因になります。
口を開けるとカクカク音がする
顎が痛くて開きにくい
顎の動きがスムーズでない
こうした症状がある方は、歯ぎしりによる顎関節の負担が関係している可能性があります。
③ 肩こり・頭痛の原因に
歯ぎしりによって 顎の筋肉が過度に緊張すると、首や肩の筋肉にも影響を及ぼします。その結果、 慢性的な肩こりや頭痛 を引き起こすことがあります。
特にデスクワークが多い方は、歯ぎしりによる筋肉の疲労が首や肩に影響を与えやすく、悪化しやすい傾向があります。
④ 歯の詰め物や被せ物が壊れる
歯ぎしりの強い力で 詰め物や被せ物が欠けたり、外れたりすることがあります。頻繁に修理が必要になると、治療費の負担も大きくなってしまいます。
また、歯ぎしりのダメージを受け続けると、将来的に インプラントやブリッジの寿命も短くなる可能性がある ため、歯科医での定期的なチェックが必要です。
⑤ 睡眠の質が低下する
歯ぎしりが強いと、 睡眠中の無意識の緊張が続き、深い眠りを妨げる原因になります。
その結果、朝起きたときに疲れが取れていない
日中に強い眠気を感じる
集中力が続かない
といった 生活の質(QOL)の低下 を招く可能性があります。
【3. 歯ぎしりの主な原因】
歯ぎしりの原因には 心理的要因や生活習慣、噛み合わせの問題など さまざまなものがあります。
① ストレス
ストレスが溜まると、無意識に歯を食いしばることが増え、歯ぎしりが悪化しやすくなります。特に、仕事や人間関係のストレスが多い方は要注意です。
② 噛み合わせの異常
噛み合わせのズレがあると、一部の歯に負担がかかり、歯ぎしりを引き起こしやすくなります。歯科医院でのチェックが必要です。
③ 生活習慣(カフェイン・アルコール・喫煙)
カフェインやアルコール、喫煙は、脳を刺激し、筋肉の緊張を高めるため、歯ぎしりを悪化させる可能性があります。
【4. 歯ぎしりの改善方法】
① ナイトガード(マウスピース)の使用
ナイトガード(専用のマウスピース)を使用することで、 歯ぎしりのダメージを軽減し、歯を保護することができます。歯科医院で自分に合ったものを作るのがおすすめです。
② ストレスをコントロールする
リラックスできる時間を作る
ヨガやストレッチを取り入れる
睡眠環境を整える
など、ストレスを軽減する工夫をしましょう。
③ 噛み合わせのチェック
噛み合わせのズレがある場合、歯科医院で適切な調整を行うことで、歯ぎしりが軽減することがあります。
④ 生活習慣の改善
カフェイン・アルコールを控えめにする
柔らかいものばかり食べず、しっかり噛む習慣をつける
など、日常生活を見直すことも大切です。
【まとめ】
歯ぎしりは 歯や顎、全身の健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、放置せずに早めの対策が重要 です。
「朝起きたときに顎が疲れている」「歯がすり減っている気がする」と感じたら、ぜひ歯科医院で相談してみてください。適切な治療や予防策を取ることで、大切な歯を守り、快適な生活を送ることができます!